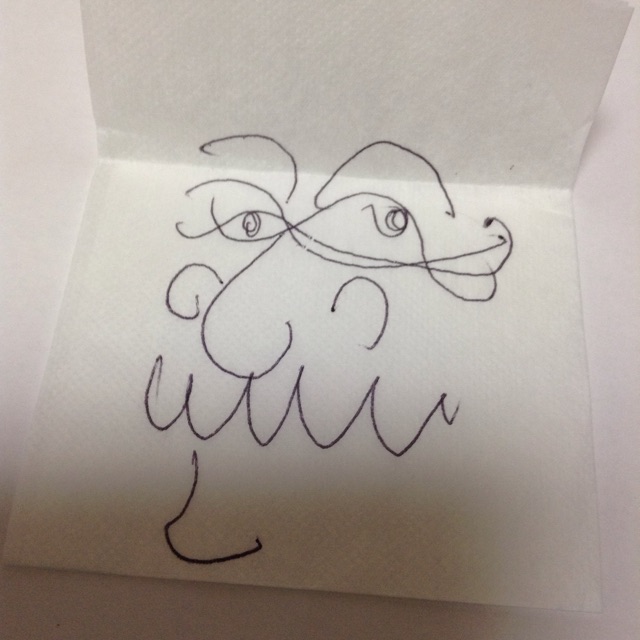じゃあ飲まなければいいじゃないかと言われるかも知れないが、そうはいかない。酒とは長い付き合いだし、酒が俺に近寄ってきて「今日はどうする」と聞いてくるほど今もいい仲だ。
もちろん飲んでひどい目にあったこともあるけれど、酒に助けられたことも何度もある。そんな損得という物差しで、酒を酒場を判断するものではないとバッカスの福音書にも書いてある。
“バッカスの福音書その3の1の4章”にこうある。
“酒の傍にいなさい。酒の力を借りなさい。されど酒には力はない。酒は汝の穴であり影である。すなわち酒の有無は無用。さあ今宵も乾杯をしなさい”とある。
要するに酒はあなた次第だということだ。その場、その時の酒が、空気が、うまいかどうかなのである。それを考えてしまうから貧乏性の俺は、酒を夕方や夜に残しておきたいのだ。
昼から酒を始めれば夜には間違いなくグタグタになっている。途中でリセット出来ないタイプなのだ。
昼に飲みたくない二つ目の理由は、叱られるからだ。
俺は今55歳で両親も健在で82歳の親父は今も毎日街場で飲んでいるし、俺が昼から飲むことにとやかく言うこともない。家内も酒のうまさをよくわかっているタイプで昼から一緒に飲むことはあってもそれを叱ることはない。
そのうえ、俺には酒場ライターという肩書きもあるので「あー、あの人は飲むのが仕事だから」と思われるぐらいで廻りからもあれこれ言われない。
けれども昼から飲むのは叱られることだと俺は思っている。だから昼から飲みたい時は寿司屋や食堂で飲んでいる。誰に対してということでもないが言い訳が出来るからだ。昼から居酒屋や立ち飲み屋に行けば言い訳できないが、そば屋やお好み焼き屋なら言い訳が出来る。
そして昼から飲まない最も大きな理由は、朝や昼から飲む酒ほどゴキゲンなことはないということを深く知っているからだ。
元旦の朝に飲むお屠蘇、一年に一度の祭が始まる前の半被に着替えてから飲む酒、棟上げの時の紺に大きな水玉の現場茶碗で飲む酒、ローマやパリの下町で飲むワイン、中南米の露天で真昼に飲むラムやテキーラ、そして誰もいない何の予定もない午後に家で飲む無頼酒。
朝や昼から飲む酒はゴキゲンの威力が凄いことを身に染みて知っているので、俺は出来るだけそれをしないようにしているのだ。
くどいようだが酒は何もしていないのだが、そこにはゴキゲンがセットになっている。もうこうなれば今から飲むしかない。あー。